そんな問題解決の一助となるのでは
と思われたかどうか分からないが、少なくとも、そんな用語を全く使わないで新約聖書を翻訳した人がいる。あのケセン語という気仙沼地方のことばで聖書の翻訳をやってのけた山浦玄嗣というお医者さんがその人。
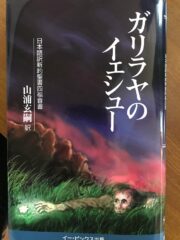
表紙絵もご本人作
ケセン語の聖書は読んでないが、その姉妹編ともいうべき”ガリラヤのイエシュー”は4福音をセケン語で訳したもの。セケンは世間のことで思わず笑ってしまうが、故郷全般のことらしい。だから、ローマ兵のセリフは鹿児島弁になっている。
「もし、旦那さア。我が家の下男が中気に罹っ、家で臥せっちょい申モしてなア、酷ムゴ、苦しんぢょい申モす。」そこで、イエシューさまはこう言いなさった。「では、わたしが参上して、お世話して差し上げましょう」(マタイ8 6-7)という具合。
セリフと書いたが、まるでドラマの台本を読んでいる感じになって楽しく読める。楽しいだけでなく、イエスさまや登場人物たちの情感みたいなものが伝わってくる。ギリシャ語をおそらく独学でマスターされたのだと思われるが半端じゃない。
あの複雑で微妙なことばの使い分けをしっかり日本語に、いやセケン語に訳されて見事なのだ。「求めなさい。そうすれば・・・」は「願って、願って、願い続けろ。そうすれば・・・」(マタイ7.7)となる。
最後にもう一つ紹介して終わりたい。「悔い改めよ、天の国は近づいた」(マタイ3.2)は「心を切り換えよ!神さまのお取り仕切りは今まさに此処にあり!」となる。注解書がなくてもみんな分かる!一読を勧めたい。

6日の野菜植えに使ったスコップたち




コメント